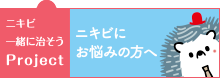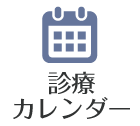アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎の原因と症状
 アトピー性皮膚炎は、遺伝的体質による皮膚のバリヤー機能異常があることに加えて、アレルギー、汗、乾燥、環境因子、心理的ストレスなどが複雑に影響して発症します。
幼少期に発症し、年齢とともに症状が軽くなる傾向がありますが、時にはそうでない場合もあります。また、大人になってから発症することもあります。
ストレスについては、思春期であれば学校での友人関係、受験、自立不安、大人になってからは仕事での人間関係が心理に影響を与え、イライラした時に掻いたり、帰宅後に人目がなくなった瞬間につい安心して掻いたり、入浴前後に儀式的に掻いて痛くなったところでおしまいにするなどの習慣がよく見受けられます。
掻く癖が自分にあるかどうかについてですが、無意識的な場合には自分でも気が付きません。そういった場合は、まず自分の手の爪を見てみてください。爪みがきのお手入れをしているわけでもないのに爪がピカピカしていませんか?このように、掻く癖が自分にあることに気がついたら、今度は少しずつその癖を減らしていくための努力をしていくだけで症状が自然に軽くなることがよくあります。
ちなみに、掻くのと同じように、皮膚をこすっている場合も症状の悪化につながるのは同じです。こすっている場合には爪はピカピカしてしていませんが皮膚科医ならすぐわかってしまいます。
とはいえ、これまでの癖をすぐにやめるのはなかなか難しいものです。一緒に減らしていく努力をしていきましょう。
アトピー性皮膚炎は、遺伝的体質による皮膚のバリヤー機能異常があることに加えて、アレルギー、汗、乾燥、環境因子、心理的ストレスなどが複雑に影響して発症します。
幼少期に発症し、年齢とともに症状が軽くなる傾向がありますが、時にはそうでない場合もあります。また、大人になってから発症することもあります。
ストレスについては、思春期であれば学校での友人関係、受験、自立不安、大人になってからは仕事での人間関係が心理に影響を与え、イライラした時に掻いたり、帰宅後に人目がなくなった瞬間につい安心して掻いたり、入浴前後に儀式的に掻いて痛くなったところでおしまいにするなどの習慣がよく見受けられます。
掻く癖が自分にあるかどうかについてですが、無意識的な場合には自分でも気が付きません。そういった場合は、まず自分の手の爪を見てみてください。爪みがきのお手入れをしているわけでもないのに爪がピカピカしていませんか?このように、掻く癖が自分にあることに気がついたら、今度は少しずつその癖を減らしていくための努力をしていくだけで症状が自然に軽くなることがよくあります。
ちなみに、掻くのと同じように、皮膚をこすっている場合も症状の悪化につながるのは同じです。こすっている場合には爪はピカピカしてしていませんが皮膚科医ならすぐわかってしまいます。
とはいえ、これまでの癖をすぐにやめるのはなかなか難しいものです。一緒に減らしていく努力をしていきましょう。
アトピー性皮膚炎の治療について
アトピー性皮膚炎の治療についてですが、症状の軽い時は保湿剤と弱いランクのステロイド外用を、湿疹の症状が強くなるにつれて中間ランクから強いランクのステロイド外用を行ってもらいます。また、かゆみの強い場合には抗アレルギー剤の内服や抗ヒスタミン剤の内服も加えます。 ステロイドのランクについては、日本皮膚科学会のホームページをご参照ください。 ▶ 日本皮膚科学会ホームページはこちら また、ステロイド以外にもタクロリムス軟膏という塗り薬もあります。しかし、タクロリムス軟膏は塗り始めのときに刺激感が出ることもあるため、上手に使えるようにご指導いたします。 これらの治療でもなかなか軽快しない重症の患者さまには、2008年から免疫抑制剤のシクロスポリンの内服治療が可能になりました。しかし、この治療は症状の強い時だけ一時的に行う治療であり、副作用の有無を厳重にチェックしながら、皮膚科専門医の指導に基づいて受けるような治療です。当院でも重症な方については血圧管理や腎機能障害などの副作用がないかの血液検査をしながら処方します。デュピクセント自己注射の治療も行っています。